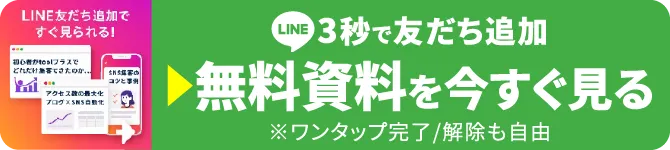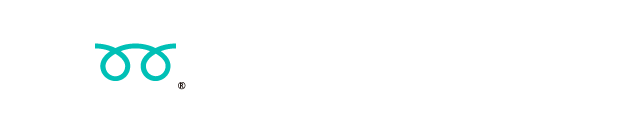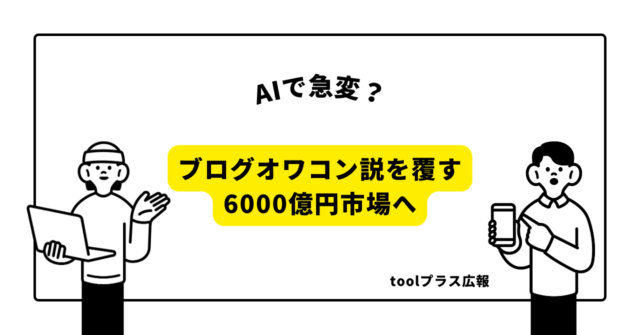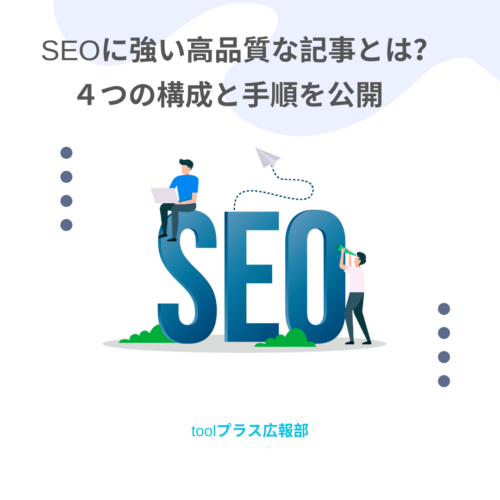WordPressなどのCMSを利用する時に「カテゴリー」と「タグ」の2機能の違いに困惑される方は大変多いのではないでしょうか。これらを適切に設定することはSEO上大変有利に働きます。
そこで本記事では、Webメディアでしばしば使われる「カテゴリー」と「タグ」の違いと適切な使い方について説明します。
目次
カテゴリーとタグのブログにおける役割
アフィリエイトブログを運営している方であれば、誰もが聞いたことのある「カテゴリー」と「タグ」。ここでは、それぞれの定義を解説します。「今までカテゴリーとタグの違いが漠然としていた」という方はぜひチェックしてみてください。
カテゴリーとは

まず、カテゴリーとは記事のジャンル分けに使われる大まかな分類のことです。
たとえば、グルメ関連のブログであれば、ラーメンのことについて書いた記事をひとまとめにし、焼肉について書いた記事を別のまとまりとしてそれぞれのカテゴリーに入れるなど、読者が読みたい記事にたどり着きやすいようにジャンルを分けることができます。
WordPressなどのCMSを使用して作成されたブログサイトでは、カテゴリーをナビゲーションメニューとして使用しているものが非常に多く見られます。
グルメ関連ブログであれば、「ラーメン」「焼肉」「和食」「洋食」などといったようにカテゴリーを設定し、閲覧者がトップページから自分の読みたいジャンルの記事を簡単に探せるようにしているものもあります。このようなブログはユーザー目線でも非常に読みやすいといえるでしょう。
タグとは
タグとは記事内で頻繁に使われるキーワードをまとめて、記事を見つけやすくするためのものです。
たとえば、グルメブログの場合は、「○○区内のランチ」や「魚を使ったお料理」など、記事の内容を端的に示すことができます。
このようにタグを設定すると、○○区内でランチを食べられるお店を探しているユーザーや魚料理の記事が読みたいユーザーが、それぞれ自分の読みたい記事にたどり着きやすくなります。
こうすることで、よりユーザーのニーズに応えることができるでしょう。
カテゴリーとタグの違い
カテゴリーとタグは上手に使いこなすことによって、非常に有効なSEO対策ができます。しかし、「どうやって使えば良いのかわからない」という声が聞かれます。そこで、このふたつの違いについて確認してみましょう。
重要度の違い
大きな違いの1つとして、重要度の優先順位が挙げられます。どちらのほうが重要度が上なのでしょうか。
一般的にブログやコンテンツ系サイトでは、カテゴリーのほうが重要度が高いとされています。なぜなら、このふたつはそれぞれ機能に違いがあるからです。
WordPressではカテゴリーは1記事につき必ず1つは設定しなければならないのに対して、タグは設定しない状態でも記事を公開することができます。(厳密には「未分類」というカテゴリーに入れることもできますが、公開したときにカテゴリー「未分類」と表示されます。)
そして、多くのサイトでは、カテゴリーが以下のようにブログカード(ブログカセット)に表示されます。

ブログの構成によっては、トップページから一目でその記事のカテゴリーが分かるようになっていることからも、カテゴリーとタグでは、カテゴリーの方が重要度が上と覚えておくと良いでしょう。
階層構造が作れるか否か
階層構造が作れるか否かも大きな違いの1つです。WordpressなどのCMSでは、カテゴリーは階層構造を作ることができますが、タグは作ることができません。
それでは、なぜタグには階層構造を作ることができないのでしょうか。それは、カテゴリーとタグはそれぞれ与えられている機能が違うからです。カテゴリーは、サイトのコンテンツを細分化するという目的に沿って作られた機能ですが、タグは、それを付与することで記事を見つけやすくすることが目的の機能です。
したがって、カテゴリー設定においては、親カテゴリーや子カテゴリーを設定することで、その記事がブログ内でどのような位置づけになっているのかを示すことができますが、タグはそれぞれが独立しています。
カテゴリーは階層構造が作れるもの、タグは階層構造が作れず、それぞれが独立した横並びのもの、と覚えましょう。
カテゴリー・タグ設定の注意点やポイント
カテゴリーとタグの違いが理解できたところで、続いては、設定の注意点やポイントについて説明します。適切に設定するとSEO対策に有効ですが、注意しないとかえってSEO上の評価が下がってしまうことがあります。
カテゴリーとタグの重複
まず、カテゴリーとタグの重複には注意が必要です。たとえば、グルメブログでカテゴリーに「ラーメン」があるにも関わらず、同じ「ラーメン」というタグを設定してしまうのはSEO上良くありません。
その他、同一の言葉をカタカナとひらがなに分けてもいけません。たとえばカテゴリーに「ラーメン」、タグに「らーめん」と表記しても、似たような言葉として扱われ、重複とみなされます。
重複すると、一覧ページのコンテンツが重複してしまうため、SEO上低評価を受けやすくなります。
カテゴリーよりも大きな範囲のタグを設定しない
カテゴリーよりも大きな範囲のタグを設定するのは、SEO上良くありません。
なぜなら、記事にタグ付けする際に、カテゴリーに含まれていない意味合いを持つキーワードを設定すると、Googleがサイトを評価する際に混乱してしまうからです。
たとえば、以下のようなタグの付け方は避けたほうが良いでしょう。
・カテゴリーが「塩ラーメン」に対して、タグが「ラーメン」
上記のような場合は、カテゴリーを「ラーメン」に設定して、タグの1つに「塩ラーメン」を設定するか、親カテゴリーを「ラーメン」、子カテゴリーを「塩ラーメン」にするのが適切です。
カテゴリーはサイト運営前に決める
設定のポイントとして、カテゴリーを設定するタイミングも非常に重要です。タグはその性質上、追加することが可能ですが、カテゴリーはサイト運営前に決めておくようにしましょう。
なぜなら、カテゴリーはGoogleにそのサイトがどのようなテーマ構成のサイトか知らせる役割があるからです。
運営するウェブサイトが何についてのサイトなのか、Googleはそのブログのカテゴリーから判断するといわれています。したがって、カテゴリーはサイトを実際に運営し始める前に設定しておくのが望ましいでしょう。
タグに固有のタイトルを含む
最後に、タグを設定する際は、タグページに固有のタイトルを含むのもポイントの1つです。
たとえば、「塩ラーメン」というタグであれば、タイトルに「古今東西のラーメンを知り尽くした男が紹介!塩ラーメン|○○のグルメブログ」といったように、検索エンジンからタグページに流入した場合も他のWebサイトと差別化できるようなタイトルが望ましいでしょう。
さらに、固有タイトルがあれば、タグから記事検索をするユーザーにとっても使いやすく、ユーザーフレンドリーなサイトを作ることができます。
まとめ
今回は、ブログにおけるカテゴリーとタグの違いと、その使い方や使用時のポイントについて解説しました。これらを適切に設定することは、SEO対策にもなり、ブログの管理も非常にしやすくなるので、まさに一石二鳥といえるでしょう。
ぜひこちらの記事を参考にして、より素晴らしいブログを作ってみてください。